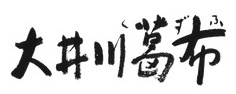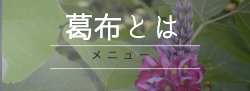葛布の事
葛布を製するは遠州掛川辺ばかりにて余国に製する事を聞かず。このほ とりの人に聞くに葛根を堀て葛粉に製する事詳しからず。
小夜の中山辺の山々に専ら生ずる蔓を取りて布に製す。
さてまた日坂の名物蕨餅と称するものは蕨にてはなく皆葛餅なり。
この葛粉はその所にて製するにあらず。
その辺の山方より製し来たるを調え、又は他国より着たれるを求めて餅 に製するなり。
日坂の人予に葛粉の製法を教えよと云いしことあり。
予はこの辺りを往来する事あまた度にして殊に遠州の地には知己多けれ ばこの葛布を織る事を委しく問いて記し置きたるを特に出すなり。
小夜の中山辺の山々に専ら生ずる蔓を取りて布に製す。
さてまた日坂の名物蕨餅と称するものは蕨にてはなく皆葛餅なり。
この葛粉はその所にて製するにあらず。
その辺の山方より製し来たるを調え、又は他国より着たれるを求めて餅 に製するなり。
日坂の人予に葛粉の製法を教えよと云いしことあり。
予はこの辺りを往来する事あまた度にして殊に遠州の地には知己多けれ ばこの葛布を織る事を委しく問いて記し置きたるを特に出すなり。
葛の蔓を刈る事
先、山に入りて蔓を刈り取り、その日釜に甑を仕掛け蒸すべし。
又は湯をたぎらしその中に漬け、ゆですぎざるようざっとゆでてよし。然して後、浅き河に漬け置く事一日一夜にして引き上げて、土間にこも を敷き、その上において上よりこもをたくさん取りかけ、又その上に青 草を切りかけ寝させて三日目の朝こもをめくり取れば、湯気たちて熱くなるなり。
この時中水を打つとて水を打ちかけ、又元の如くして一日置いて引き上 げ、河へ持ち行きよく踏み洗い上皮を去り、家に持ち帰りて皮を剥ぎ、 元末交じらざるよう揃えくくり、竹にかけて干しあぐるなり。
又皮を去り、洗いて白水に一日一夜浸し置き河にて洗うべし。
この中水を打つ事は大事にてこれをせざれば苧○るといえり。
糸の製(しかた)
干しあげたる苧を程よく裂きて、悉く女の糸結びに結び継ぎて、継ぎ目 の角を鋏にて切り、苧桶に繰り入れ繰り入れして置き、糸にせんと思う とき水を吹きかけ又は水に暫し漬けよく水を切り、それより車にかけて よりをかけ管になして織るなり。(葛布というはみな経は木綿糸にして 緯は葛の糸を織り入れたるなり)
◆女将より
ここで、私には大いに疑問が生じます。
製葛録によると、緯の葛はよりをかけるとあります。
ところが我々の知る限り、掛川、日坂、金谷ではよりをかけたものは
作っておりませんでした。
経は木綿で、製葛録でいうところと同じですが、緯はよりかけをしない 糸を、それも出来るだけ平らな面がでるようにそっと筬で引き寄せるよ うに織るのです。うちの親方は私の織ったものを見て「平を出せ。平を 出せ。」とよくいいます。
しかも現代の遠州地方では、杼(ひ)から糸が出る時自然にかかるより を防ぐため、わざわざツグリという特殊な糸状をつくります。
製葛録が書かれたのは江戸末期、1820年頃と考えると、一体だれが 何時何故よりかけする事をやめ、わざわざ平が出る織り方に変えたの か、謎は深まります。
ちなみに私どもが集めた江戸時代のものと思われる葛布の道中合羽、
裃、袴等は全てよりかけしていないものでした。
日本民芸館の収蔵品も全てよりかけなしのものでした。
しかし、ここで大きな福音が九州の甑島に残されています。
甑島ではごく最近迄経緯よりかけした着物が織られており、そのうち数 店が島の博物館に収められているとの事。
来年は、甑島へ行くぞ〜。
よりをかければ強くなる。よりをかけなければ美しい艶がでる。
今私の手元にある葛布の道中着は、用と美のぎりぎりのせめぎあいの中 で生まれた産物、と言えはしないでしょうか?

一反の緯(葛糸)掛目五十目あたり
一反の経の木綿糸は片羽入れなり これを平織りという
長尺というは上下地のことなり
一反の緯(葛糸)掛目七十目
一反の経諸羽八ツ事の筬に入るなり これを諸織という
その他合羽地等はこれに準じて織るものなり。
極上は苧のよきところを細く裂き継ぎて経糸も吟味して織るなり。
木綿を織る如くはた糸にて経をこしらえ緯に葛苧を織るなり。
総てに木綿を織るに同じ。
尤も葛糸は結び継たるもの故織りたる裏表に結び角出るなり。
面は織る程で鋏をもて切り取り、裏は織り上げて切るべし。
上品下品は糸の仕様にてはかるなり。
一 諸織の極上の上下地 白地にて一反
金弐部弐朱位
下品は金壱分弐朱位
一 同 染袴地壱反 多く花色なり
金壱分前後
下品は銀十三匁
一 平織袴地一反に付
銀十匁位
下品は銀八九匁
右は掛川にて調取の値段なり。
それ葛布はいずくにても出来ざる事はあらざれども、只その事とばかり 思いて、前にもいう如く遠州にては根を堀りて葛粉とすることまれにし て、他方より求めて用い、九州などにては蔓をとりて布に織る事は聞く ながら、これを織り見んともせずして葛布を求めて用いぬ。
みな心を深く用いざるによりてなり。
又飢饉は世の病にて何時の年とも察しがたきものなれば、百姓にては明 年は飢饉なるべしと覚悟するをよき心得の農人とも云うべし。
武家方にて太平に武を忘れじと云えるに同じかるべし。
享保子年などの飢饉を伝え聞くに松の木の肌を削りて餅とし、色々の木 の実、草の実等を製して食せりと聞き及べり。
ここに知るに葛は前文にも云う如く清らかにして毒なく野山に生じ、飢 饉の備えにはこれに勝るものはあらじ。
この事のなき国にてははやくもこの業せんようを長たる人より教えたま
わん事を希うになん。
製葛録 終
◆女将より
これで製葛録の全文を終わります。
遠州では葛粉を取ることをせず、只布にばかり製して商っていた。
しかも、全国的に見ると葛布を織るところは外にもあったに違いないの だけれども、他所は主に自家用ばかりだったらしいこと。
それでは何故遠州ばかりが一大葛布の生産地だったのでしょうか。
今でも産地は、粟ン岳(あわんたけ)というこの辺で一番高い山を臨め る金谷、日坂、掛川に限られています。
又、製葛録本文にもあった小夜の中山というのも金谷と日坂の間の東海 道沿いにあるところですし、昔掛川の人が葛糸を注文して作ってもらっ ていた倉見というところも粟ン岳の麓にあります。
実は、最近前のブログでも紹介した事任(ことのまま)神社の宮司様か ら興味深い話をうかがいました。
このお社の本当のご神体は粟ン岳で、神社北側の小高い森の頂上から粟 ン岳を遥拝するというのです。
そして、粟ン岳の粟は阿波に通じ、今から1800年程前に阿波忌部が 海伝いに阿波よりこの岳付近にやってきて色々な神事や業を伝えたらし いのです。
さあ、阿波忌部氏と粟ン岳、葛布の不思議な物語の始まりです。なんだ かわくわくしますね。
この神秘については、次回ブログで委しく考察したいと思います。
トップに戻る